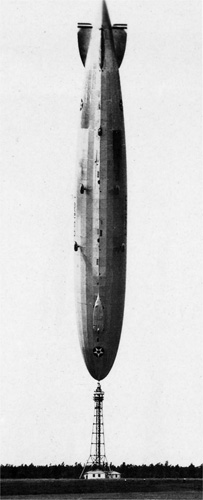飛行船用格納庫
飛行船航空振興会社(Gesellschaft zur Frderung der Luftschiffahrt)が、ツェッペリン伯爵の最初の飛行船建造のために1899年にフリードリッヒスハーフェンのマンツェルに水上格納庫を建造したことはよく知られている。しかし「LZ1」の実験終了後、長さ130m、幅25m、高さ25mの格納庫は飛行船と同様解体され、会社は清算された。従って「LZ2」を建造するために、同じくマンツェルに長さ140m、幅26m、高さ25mの水上格納庫を1903年に建造した。1906年に初飛行した「LZ2」と「LZ3」はこの格納庫で組み立てられたと思われる。メーアスブルクにあるウーバン氏のツェッペリン博物館の発行している「ツェッペリン・クーリエ」2006年版によれば1907年に同じマンツェルに1903年に建造されたものとほぼ同じ寸法の格納庫が建造されているが、水上格納庫か陸上に建設されたものか判らない。
同誌によると1906〜09年にかけて、ベルリンのライニケンドルフ(2棟)、テーゲル、ライプチッヒの北にあるビットフェルト、ケルンのニッペス、その北のライヒリンゲンなどに長さ7〜80mの短い格納庫が建設されているようである。高さ、幅とも概ねフルサイズの格納庫と似たようなものであり、飛行船の中央部のみを収容する目的だったのであろうか、よく判らない。この種の格納庫は1913年以降建造されていないようである。
1908年にはフリードリッヒスハーフェンに長さ145m、幅28mの格納庫が建てられ、翌年には別の場所に長さ178m、幅46mの大きな格納庫が建設されている。
エヒターディンゲンの事故の後、ドイツ国内から寄せられた醵金で1908年9月にツェッペリン飛行船製造社が設立された。企業経営能力と事業開発の企画力に優れたアルフレート・コルスマンが尽力して翌年11月にドイツ飛行船運輸会社(DELAG)を設立し社長となって「LZ10:シュヴァーベン」「LZ11:ヴィクトリア・ルイゼ」「LZ13:ハンザ」「LZ17:ザクセン」を建造し飛行船事業に見通しをつけた。エッケナー博士が広報担当役員としてこれに参加し4年間にわたって地方各都市の市長に精力的に広報活動を行った結果、ドイツ各地に飛行船格納庫が建設された。
1909年にはケルンのビッケンドルフに長さ190m、幅40mの大格納庫、マンハイムに長さ137m、幅26m、メッツに長さ150m、幅40mの格納庫などが建設された。翌年にはバーデン・オース、ベルリン、デュッセルドルフ、フランクフルト、ゴータ、ヨハニスタールなどに続々と飛行船格納庫の建設が続いた。
長さが200mを越える格納庫が建設されるのは1914年のフリードリッヒスハーフェン第2格納庫からであり、世界大戦間近の1915年になると北部を中心にノルトホルツ、トンデルンをはじめとする軍事用格納庫の建設が多忙を極めた。
1916年にベルリン・シュターケンに作られたツェッペリン新工場の格納庫では飛行船ばかりでなくツェッペリン社製の大型爆撃機の生産も開始された。
1936年にフランクフルトに「LZ129:ヒンデンブルク」北米定期便のために建造された長さ275m、幅52mの大格納庫や、フリードリッヒスハーフェンの第5格納庫が建設されるまでにドイツ国内で建設された格納庫は大小あわせて約90棟に及び、このほかにアフリカ飛行の際に使われたブルガリアのヤンボリの格納庫、「LZ129:ヒンデンブルク」のためにブラジルのサンタクルスに建造された270mの格納庫などドイツ国外に建設されたものを含むと100棟に近くなる。
ちなみに霞ヶ浦の海軍航空隊に移設された格納庫は1916年に建造されたユッターボック第2格納庫で、これを移設する際に追浜にあった横須賀航空隊は飛行機と併存するには狭すぎたのでこの機会に移転されたのである。
秋本実著「日本飛行船物語」によれば起工式は大正11年9月4日に挙行された。関東大震災の大正12年9月1日には屋根のスレート葺きが行われていたが、昼食のため作業員が地上に降りた直後で転落事故はなかったという。